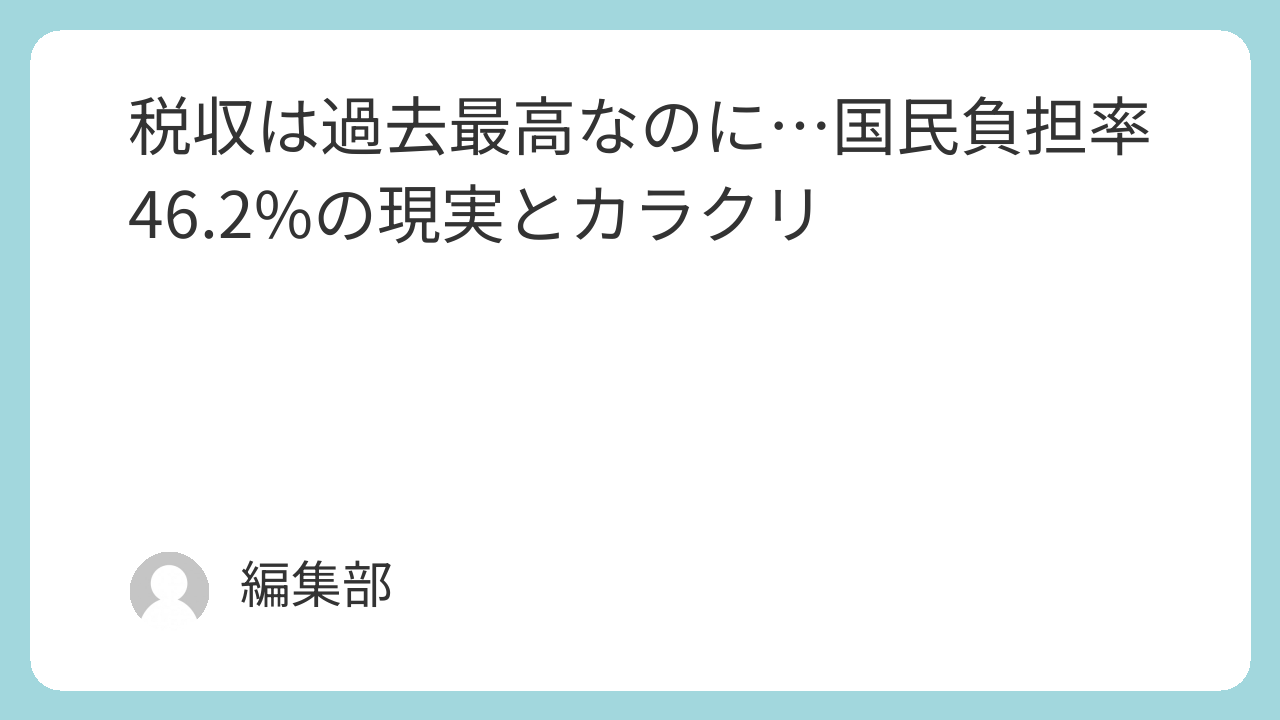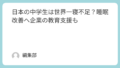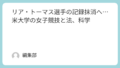このニュースが報じられた年月日
2025年7月2日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
- 時事ドットコム: 国の税収、5年連続最高=75.2兆円、法人税伸びる―24年度
- 財務省: 令和7年度の国民負担率を公表します
- 税理士法人山田&パートナーズ: 財務省発表 令和7年度国民負担率、46.2%に
このニュースの3つのポイント
- 国の税収は企業の好業績を背景に5年連続で過去最高を更新する見通しである。
- 一方で、税金と社会保険料を合わせた「国民負担率」は46.2%と高い水準で推移している。
- 税収増の主因は法人税であり、個人の所得税収は伸び悩んでいるため、多くの人が豊かさを実感しにくい構造になっている。
事件の概要
財務省は、2024年度の国の税収が5年連続で過去最高を更新し、75.2兆円に達する見込みだと発表しました。しかし、多くの国民が景気回復や豊かさを実感できずにいます。その背景には、税収増の内訳と、税金に加えて社会保険料の負担も考慮した「国民負担率」という指標に隠されたカラクリがありました。
事件の背景と解説
「国の税収が過去最高」というニュースを聞いても、なぜ私たちの生活は楽にならないのでしょうか。その答えは、税収の内訳と、もう一つの重要な指標「国民負担率」にあります。
まず、税収増を牽引しているのは、個人の給与から天引きされる所得税ではなく、企業の利益にかかる「法人税」です。財務省の統計を見ると、企業の売上や経常利益は好調で、これが法人税収を押し上げています。
一方で、所得税収は伸び悩んでおり、企業の好業績が個人の賃金上昇に十分結びついていない現実を反映しています。
これが「国の財政は潤っているのに、個人の可処分所得は増えない」という実感とのギャップを生む最大の要因です。
次に、私たちの負担は税金だけではありません。財務省が公表する「国民負担率」は、国民所得に占める税金と年金・医療などの社会保障負担の合計割合を示す指標です。令和7年度の見通しでは46.2%と、所得の半分近くが公的な負担で占められる計算になります。このうち社会保障負担は18.0%を占め、少子高齢化の進展に伴い、構造的に増加し続ける傾向にあります。
さらに、この数字には国の借金である「財政赤字」は含まれていません。財政赤字(将来世代が払うべき税金)まで加味した「潜在的国民負担率」は48.8%に達します。
国の財政が好調に見えても、個人レベルでは社会保険料という固定費が増え続け、将来への不安も残る。このような構造を理解することが、現代日本の経済を正しく見る上で不可欠と言えるでしょう。個々人が資産形成や適切な保険への加入を考える重要性が増している背景でもあります。
登場するおもな固有名詞
- 財務省: 財務省
- 法人税: 法人税(国税庁)
- 国民負担率: 国民負担率の推移(財務省)
この事件をより深く知るための関連情報
- 法人企業統計調査: 法人企業統計調査(財務省)
- 我が国の財政事情: 図表で見る日本の財政(財務省)
まとめ
国の税収が過去最高を記録した背景には、好調な企業業績による法人税の増加があります。しかし、個人の所得の伸びはそれに追いついておらず、さらに増加し続ける社会保障負担が家計を圧迫しています。このため、多くの人が豊かさを実感しにくい状況が続いており、マクロ経済の指標と個人の生活実感との間に大きな乖離が生まれています。
【免責事項】 この記事は、AI(人工知能)を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。