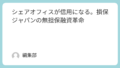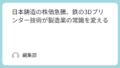このニュースが報じられた年月日
2025年07月02日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
訂正対象と思われる記事
読売新聞オンライン:[スキャナー]日米財務相会談、市場に配慮し為替目標設定棚上げ…日本は次の強硬「ディール」警戒(訂正あり)
このニュースの3つのポイント
- 読売新聞社が、日米財務相会談に関する4月26日付の報道内容が誤りだったとして、7月2日付の朝刊で訂正・謝罪した。
- 誤報は、ベセント米財務長官が加藤財務大臣に対し「ドル安・円高が望ましい」と述べたとするもので、為替市場に大きな影響を与えかねない内容だった。
- 実際には、会談で為替レートの具体的な水準に関する発言はなく、今回の件は金融報道の正確性とメディアの社会的責任の重さを浮き彫りにした。
事件の概要
2025年7月2日、読売新聞社は、4月26日の朝刊に掲載した日米為替協議に関する記事に誤りがあったとして訂正記事を掲載しました 。問題の記事は、4月25日に行われた日本の加藤勝信財務大臣と米国のスコット・ベッセント財務長官の会談で、ベセント長官が「ドル安・円高が望ましい」と発言したと報じたものです。この報道に対し、財務省は「事実無根」として強く抗議していました 。
事件の背景と解説
この誤報問題の核心を理解するには、国際金融の世界における「言葉の重み」を知る必要があります。特に、為替相場は各国の経済政策や要人発言に敏感に反応するため、その報道には極めて高い正確性が求められます。
問題となった会談は4月25日に行われ、その後に発表された公式内容では、為替レートは市場で決まることや、過度な変動は望ましくないといった、従来からの原則的な立場を再確認するにとどまっていました 。為替レートの具体的な水準目標に言及するような踏み込んだ発言は一切ありませんでした。
しかし、翌26日の読売新聞は、米財務長官が「ドル安・円高」を望んだと断定的に報じました 。これは、政府や中央銀行の要人が発言によって市場を特定の方向に誘導しようとする「口先介入」と呼ばれる行為に相当します 。もし事実であれば、世界中の投資家がドルを売って円を買う動きを加速させ、金融市場に大きな混乱を引き起こしかねない、極めて重大な発言です。実際、報道があった4月26日の為替レートは1ドル144円前後で推移しており、このような発言は市場の方向性を一変させる力を持っていました 。
財務省が「事実無根」と強く抗議し、最終的に読売新聞が誤りを認めて訂正したことで、この記事が何らかの取材・確認プロセスの誤りから生まれたものだったことが明らかになりました。この一件は、一つの報道が金融市場や企業の経済活動、ひいては個人の資産にまで影響を及ぼす可能性があることを示しています。金融や経済に関する報道がいかに慎重な裏付けを必要とするか、そしてその誤りがもたらす影響の大きさを、社会全体が改めて認識する契機となりました。
登場するおもな固有名詞
- 読売新聞社: 読売新聞グループ本社
- 財務省: 財務省
- 加藤勝信: 公式X(読売新聞の訂正記事を受けた投稿にリンク)
- スコット・ベッセント:(Scott Bessent(英語版Wikipedia))
この事件をより深く知るための関連情報
- 口先介入とは: 口先介入(くちさきかいにゅう)とは|意味・事例・よくある質問
- 報道倫理と誤報: マスコミ不祥事 (Wikipedia)
まとめ
今回の読売新聞による誤報と訂正は、単なる記事の間違いにとどまらず、金融市場の安定と報道機関の信頼性という二つの重要なテーマを浮き彫りにしました。政府要人の発言が持つ影響力と、それを伝えるメディアの責任の重さを改めて示す事例として、今後の報道のあり方を考える上で重要な教訓となるでしょう。
【免責事項】 この記事は、AI(人工知能)を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。