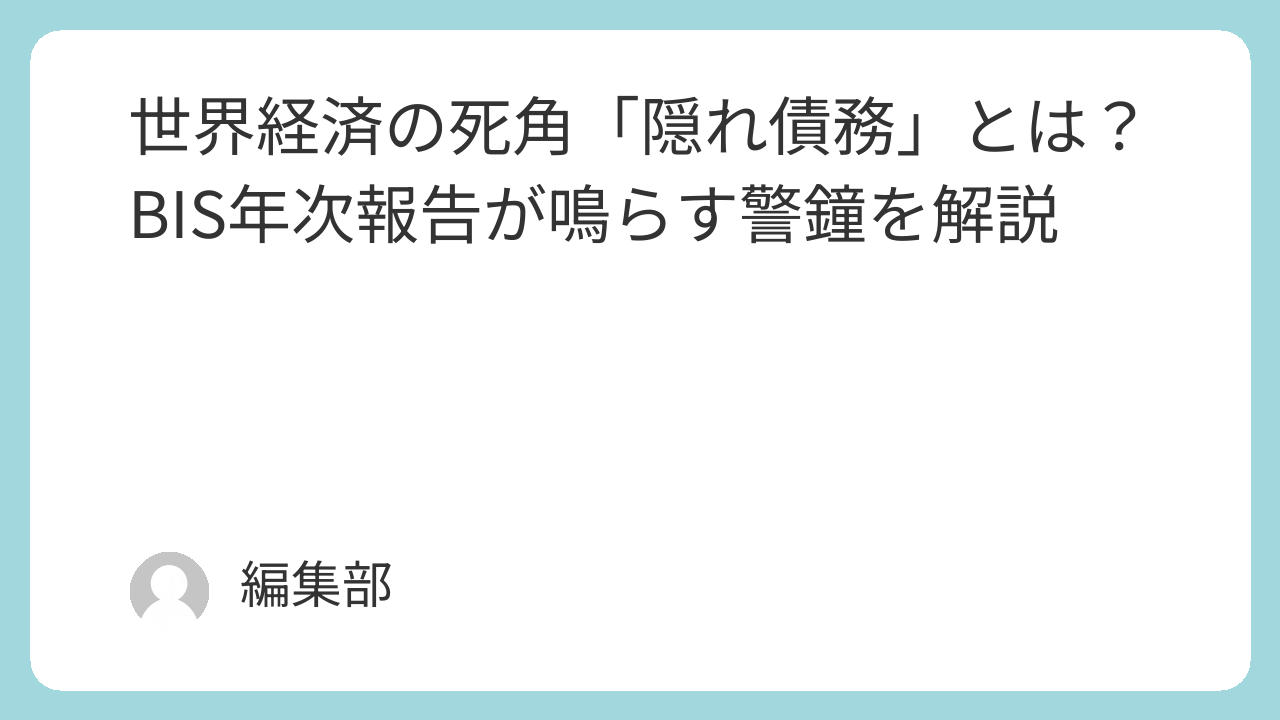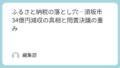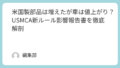このニュースが報じられた年月日
2025年7月3日
同じニュースを報じている記事一覧とリンク
- 日本経済新聞: 米ドル「隠れ債務」が1.4京円、BISが警鐘 金融危機の火種に
- 麗澤大学 (日本経済新聞掲載情報): 【メディア掲載】経済学部 中島真志教授のコメントが日本経済新聞に掲載されました
- ABA Banking Journal:(BIS economic report: Prospects for global economy more uncertain)
- 国際決済銀行:(https://www.bis.org/index.htm)
このニュースの3つのポイント
- 「中央銀行のための中央銀行」と呼ばれる国際決済銀行(BIS)が、世界経済の見通しは不確実性が増していると警告した。
- 金融・決済システムの専門家である麗澤大学の中島真志教授は、BISが問題視する「隠れ債務」の膨張に言及した。
- この「隠れ債務」は、主に銀行以外の金融機関が利用する為替スワップなどから生じ、従来の統計では把握しきれない巨大なリスクとなっている。
事件の概要
スイスに本部を置く国際決済銀行(BIS)が2025年の年次経済報告書を公表し、世界経済は貿易摩擦や財政規律の緩みなどから不確実性を増していると警鐘を鳴らしました 。この報告書に関連し、日本の金融・決済システムの専門家である麗澤大学の中島真志教授は、BISが特に問題視している「隠れ債務」の膨張についてコメントしており、水面下で巨大化する新たな金融リスクへの注目が集まっています 。
事件の背景と解説
このニュースを深く理解するには、「BISとは何か」という組織の重要性と、彼らが警告する「隠れ債務」という専門的な概念の正体を解き明かす必要があります。
まず、国際決済銀行(BIS)は、単なる研究機関ではありません。「中央銀行のための中央銀行」とも呼ばれ、世界各国の金融政策を司る中央銀行(日本の日本銀行、米国のFRBなど)のトップが定期的に集まり、国際的な金融システムの安定について議論する場です 。そのため、BISが公表する報告書は、単なる一組織の見解ではなく、世界の金融政策決定者たちの共通認識や懸念を色濃く反映したものと言えます 。BISが「リスクがある」と指摘することは、世界の金融界のトップたちがその問題に強い危機感を抱いていることの表れであり、極めて重要度が高い情報なのです。
次に、そのBISが警告する「隠れ債務」の正体です。これは主に、銀行以外の金融機関(年金基金や保険会社など)が利用する「為替スワップ」などのデリバティブ取引から生まれます。例えば、ある日本の機関投資家が米ドル建ての資産に投資したいが、手元には円しかないとします。その際、銀行から米ドルを借り入れる(これは貸借対照表に「負債」として記録される)代わりに、為替スワップを利用します。これは、一時的に円とドルを交換し、将来の特定の日にあらかじめ決めたレートで買い戻す(円を渡してドルを返してもらう)契約です。この「将来ドルを返済する義務」は実質的にドル建ての借金と同じですが、現在の会計基準では多くの場合、デリバティブ取引として扱われ、バランスシート上の「負債」として計上されません。これが「隠れ債務」と呼ばれる所以です。BISの試算では、この統計に表れない世界のドル建て債務は数十兆ドル規模に達するとも言われ、金融危機時には、すべての市場参加者がこの「隠れた約束」を果たすために一斉にドルを求め、深刻なドル不足(クレジットクランチ)を引き起こす巨大なシステミックリスクとなり得ると懸念されています。
登場するおもな固有名詞
- 国際決済銀行 (BIS):(https://www.bis.org/)
- 麗澤大学:(https://www.reitaku-u.ac.jp/)
- 中島真志: 麗澤大学 教員紹介 中島真志
この事件をより深く知るための関連情報
- 為替スワップ: 為替スワップ – Wikipedia
- 金融システム: 金融市場インフラとは何ですか? – 日本銀行
まとめ
BISによる「隠れ債務」への警告は、現代のグローバル金融システムが抱える、目に見えにくいが故に深刻なリスクを浮き彫りにしています。金融技術の高度化は効率性を生む一方で、規制や統計が追いつかない新たな脆弱性を生み出します。この問題は、金融当局にとって、銀行以外の金融セクターに対する監督と透明性の確保が、将来の金融危機を防ぐ上でいかに重要であるかを再認識させるものと言えるでしょう。
【免責事項】 この記事は、AI(人工知能)を活用して作成されています。細心の注意を払い、最終的に人間の目で可能な限りチェックしていますが、内容に誤りが含まれる可能性があります。情報の正確性については、必ず出典元などの一次情報をご確認いただくようお願いいたします。